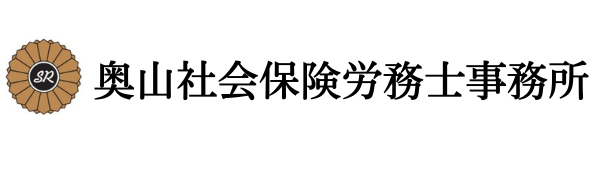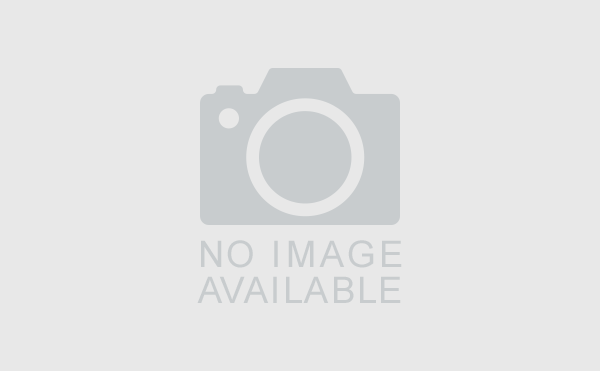事務所だより(2025年11月)
1.19~23歳未満の健康保険の被扶養者要件が変更になりました
2025年10月1日より、健康保険で被扶養者として認定を受ける家族が19歳以上23歳未満の場合、年間収入要件が「130万円未満」から「150万円未満」に引き上げられました。
これは、令和7年度税制改正における「特定扶養控除の見直し」に対応したもので、若年層の就業調整緩和や人手不足対策を目的としています。
従来、健康保険の被扶養者認定では、60歳未満の家族については年間収入が130万円未満であることが要件でした。
改正後は、認定を受ける日が2025年10月1日以降で、かつその年の12月31日時点で19歳以上23歳未満の家族に限り、年間収入要件が150万円未満に緩和されます。
ただし、この変更はあくまで被保険者の配偶者を除く家族が対象であり、他の要件(同居・仕送り等)は従来どおりです。
年齢判定は、その年の12月31日時点の年齢で判断します。例えば、2026年11月に19歳を迎える場合は、2026年の年間収入要件は150万円未満。
一方、2026年11月に23歳になる場合は、その年は130万円未満となります。誕生日の前日に年齢が加算される点にも注意が必要です。
また、健康保険での「収入」には、所得税法上の非課税扱いとなる通勤手当や食事手当なども含まれます。
税法と社会保険では取扱いが異なるため、誤解を防ぐために従業員への周知や社内説明文の整備が重要です。
今後、全国健康保険協会(協会けんぽ)では10~11月にかけて被扶養者資格の一斉調査が行われます。
今回の改正を踏まえ、対象者の収入や勤務実態を改めて確認しておくことをお勧めします。
制度の詳細については、以下のリンクをご確認ください。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2025/202508/0819.html
2.労災保険で通院交通費は支給される? ― 「移送費」について
労災保険には「移送費」という給付があり、治療や通院に必要な交通費が補償の対象になる場合があります。
救急搬送時だけでなく、通院にかかる交通費も一定の条件を満たせば支給されます。労働者が安心して治療に専念できるように設けられた制度です。
ただし、単に本人の希望による遠方受診は対象外であり、「医学的にその医療機関での治療が必要」と認められることが前提です。
たとえば、近隣に労災指定病院がない場合や、専門的な治療が必要なケースでは、遠方への通院でも移送費が認められる可能性があります。
認められるためのポイントは「合理的な必要性」があるかどうかです。
公共交通機関を利用した場合は実費が支給され、自家用車の場合は走行距離に応じて1kmあたり37円が基準とされています。
タクシーは原則対象外ですが、公共交通の利用が難しい、あるいは医師の指示がある場合に限り、領収書を添付すれば認められることがあります。
なお、駐車場料金や宿泊費は対象外です。
請求は「療養補償給付たる療養の費用請求書(様式第7号)」の移送費欄に、通院区間や回数、距離を記載して行います。
自家用車利用時は走行距離を記録しておくとスムーズです。
労働基準監督署によって求められる添付資料が異なる場合もあるため、提出前に確認しておくと安心です。
従業員が遠方の専門医への通院を余儀なくされた場合、「通院費も労災の移送費として請求できる可能性がある」ことを早めに案内しておくと良いでしょう。
制度の仕組みを知っておくことで、従業員の負担を軽減し、会社としても円滑かつ誠実な労災対応につながります。
実務対応で不明な場合はお気軽にお問い合わせください。