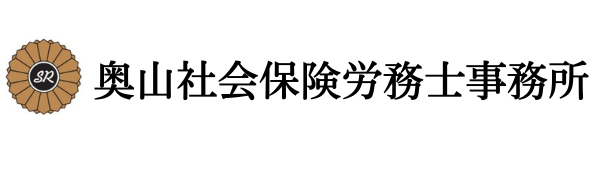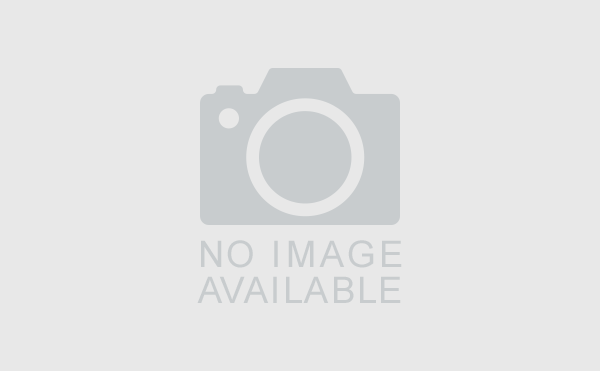事務所だより(2025年10月)
1.「令和6年度使用者による障害者虐待の状況等」の結果を公表
厚生労働省は、「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」(障害者虐待防止法)第28条に基づき、令和6年度における使用者による障害者虐待の状況等を公表しました。
報告によれば、令和6年度に通報・届出のあった事業所は1,593か所、対象となった障害者は1,827人でした。そのうち虐待と認められたのは434事業所、652人であり、前年度と比較すると減少傾向がみられます。一方で通報・届出数は増加しており、職場における虐待の把握や通報意識の向上が進んでいるものと考えられます。
虐待の内容を種別でみると、経済的虐待が584人と最も多く、心理的虐待、身体的虐待、放置等、性的虐待が続きました。特に経済的虐待は全体の約8割を占め、賃金や財産管理に関する適正な取扱いが依然として大きな課題であることが示されています。
障害者虐待防止法は、使用者に対し障害者への虐待を防止する義務を課すとともに、虐待が疑われる場合の通報義務を定めています。また、使用者が虐待を行った場合には、行政による指導や改善命令の対象となるほか、刑事罰が科される場合もあります。事業所は、内部体制の整備、従業員教育の徹底、通報窓口の明確化など、再発防止策を講じることが求められます。
企業における障害者雇用の推進と職場環境の改善は、今後の人材雇用の大きなテーマの一つと感じます。公表資料を見ると虐待に対して労働局が講じた措置として最低賃金法に基づく指導等も確認できます。10月からの最低賃金の見直しと合わせご参考にしていただけますと幸いに存じます。 ※検索キーワード厚生労働省・ 令和6年度使用者による障害者虐待の状況等です
2.10月からの改正育児・介護休業法
本ニュースレター2025年4月号(vol.225)でお伝え致しましたが、10月より、改正育児・介護休業法の改正が行われます。企業に対して「育児期の柔軟な働き方」の提供が義務化され、3歳以上小学校就学前の子を養育する労働者に対し、仕事と育児の両立を支援するための制度の導入が求められます。また、労働者への周知や意向確認も行うこととされます。
「育児期の柔軟な働き方」は、具体的には、企業は以下の5つの措置のうち、少なくとも2つ以上を制度として整備し、提供する必要があります。また措置を選択する際は、過半数組合等からの意見聴取の機会を設ける必要があります。
①時差出勤・フレックスタイム制度、②テレワーク制度(10日以上/月)、③保育施設の設置・運営(ベビーシッターの手配および費用負担なども含む)、④就業しつつ子を養育することを容易にするための休暇の付与(養育両立支援休暇短時間勤務制度…10日以上/年)、⑤短時間勤務制度
これらの選択した措置については、3歳未満の子を養育する労働者に対して、周知と意向確認を個別に行うこととなります。また、労働者が本人または配偶者の妊娠・出産等を申し出た時と、子が3歳になるまでの適切な時期に、労働者の意向を個別に聴取することも義務となりました。これらの周知や意向確認については、行う時期、周知や聴取を行う事項、方法についても示されています。
これまで3歳未満の子を対象とした短時間勤務制度はありましたが、今回の改正では対象年齢が引き上げられ、より広範な育児期に対応する制度整備が求められます。企業としては、就業規則の改訂、制度導入に伴う社内調整、対象者への周知・相談体制の整備など、実務対応が急務となります。ご不明な点は、社会保険労務士にご相談下さい。