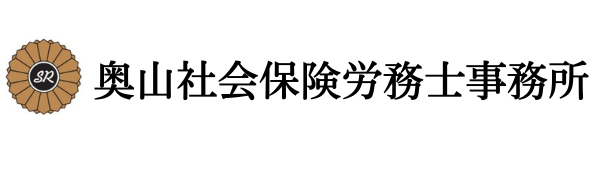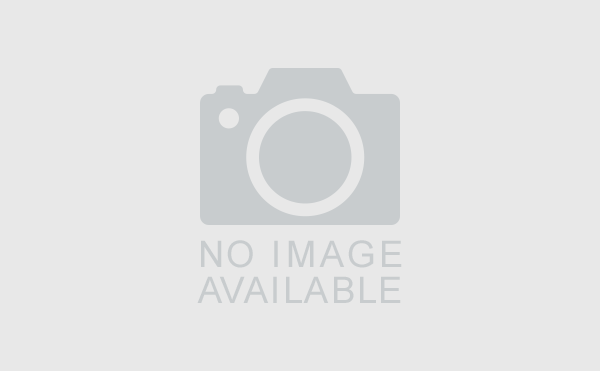事務所だより(2025年9月)
1.令和7年度地域別最低賃金額改定の目安
8月4日に開催された中央最低賃金審議会で、令和7年度の地域別最低賃金額改定の目安について答申が取りまとめられました。
答申のポイントは、都道府県の経済実態に応じて、全都道府県をA、B、Cの3ランクに分けて、引上げ額の目安を提示していますが、埼玉、千葉、東京、神奈川、愛知、大阪の6都府県のAランクで63円、北海道、茨城、栃木、群馬、山梨、京都、広島、福岡などの28道府県のBランクで63円、青森、鳥取、高知、大分、沖縄などの13県のCランクで64円の増と,引上げ額の目安を掲示しています。A、B、Cの3ランクに分けていますが、A、Bは同一金額でCは1円高いということです。
今後は、各地方最低賃金審議会でこの答申を参考にして、地域における賃金実態調査や参考人の意見等も踏まえた調査審議の上で答申をおこない、各都道府県労働局長が地域別最低賃金額を決定することとなりますが、目安どおりに引き上げがおこなわれた場合には、東京都の新しい最低賃金額は1,226円、神奈川県は1,225円、埼玉県は1,141円、千葉県は1,139円になります。
仮に全都道府県で目安どおりに引き上げがおこなわれたれた場合の全国加重平均は1,118円で、上昇額は63円(昨年度は51円)となり、昭和53年度に目安制度が始まって以降で最高額となります。引上げ率に換算すると6.0%(昨年度は5..1%)となります。各都道府県の最低賃金の発効年月日は10月1日以降順次にとなりますが目安どおりにとなるのでしょうか。
2.勤怠を正しくつけることについて
労働者名簿、賃金台帳、出勤簿は法定3帳簿と言われていて労働者を雇う以上、会社は備えておく必要があります。
この中で出勤簿は労働者が出勤してくる日は毎日つけるものですので一番面倒なもののように見えます。ですが、出勤簿を正しくつけることは労務管理の基本であり、労務トラブル回避の基となるのでなんとか対応していきたいものです。
また賃金は1分単位で計算することが求められます。紙の出勤簿と電卓だけで給与計算していたころは煩雑となることから15分単位で勤怠をつけたり給与計算することも黙認というか、そんなこともあったと聞きますが、勤怠をつけることや給与計算もクラウドのソフトがこれだけ出てきますと現代では1分単位でなぜ計算できないのかということになっています。
勤怠を正しくつけないと、労働者から残業代を請求されたときに会社としては何も反論できなくなります。よく聞くのが『残業してもらったこともあったがそれ以上に定時前に直帰することを認めていた』という会社側の反論です。これも勤怠をきちんとつけていれば通ることもありますが、勤怠をつけていなければ全く通らない話です。
もちろん勤怠は事実に即してつける必要があります。たまに出勤時刻9時00分、退勤時刻18時00分が1ヶ月間、毎日1分も違わずズラッと並んだ出勤簿にお目にかかりますがこれは会社に来たことの証明にはなるかもですが、事実と言えるでしょうか。労働者側から退勤時刻は●時●分だったといわれれば、おそらく労働者側の主張が採用されます。
勤怠を1分単位でつけるソフトは多く出ています。会計ソフトを契約していれば5名までは給与計算と勤怠管理を無料で使えるなんていうのもあります。もし勤怠を事実に即してつけていない場合、その習慣を変えることはパワーのかかることですがトラブルになる前になんとか対応いただければと思います。